“出どころによる判断” のトリック
ある主張や作品をそれ自体において先入観なく吟味して評価するのではなく、そうした主張や作品の出どころによって判断を下し、その判断を正当なものとして相手に受け入れさせようとすること。
たとえば、ある新聞記事があった場合、その内容をには踏み込まず、その新聞社に対する主観的な先入観によってその記事自体を判断するようなケースである。「朝日新聞が言っているのを鵜呑みにしてるんですか?」 などなど。
あるブログ記事があった場合、その内容には踏み込まず、そのブログサイトに対する主観的な先入観によって当のブログ記事自体を判断するケースである。同性婚問題についての主張に対し、「このブログ主は原発肯定派じゃないですか。」 などなど。
また、ある主張、意見があった場合、それらの内容をには踏み込まず、その主張者に対する主観的な先入観によって当の主張や意見自体を判断するケースである。「あなたはサラリーマンでしょ。サラリーマンの言いそうなことですね。」 などなど。
こうした判断は必ずしも否定的なものばかりではない。逆に肯定的な場合も多々ある。たとえば、「この製品を売っている会社は長年東芝の子会社ですから」 とか、「これはとにかく弁護士先生が言っているわけですから」 というふうに高評価の根拠とする場合もよくある。
いずれも本来の対象の中に入り込んでの内在的な吟味、検証というプロセスを経ずに、当の対象に対して外面的な要素によって一方的に安易に主観的な判断を下すものである。
誰々が言っているのなら当てにならない、信頼性がない、という否定的なケースが多いが、逆に、誰々が言っているのなら大丈夫だ、信用できる、といった肯定的なものも結構あるのだ。
共通しているのは、当の対象を正当に吟味、検証するという手間を省いて、安易に外面的な先入観を根拠に判断を下している点である。
ある映画作品があった場合、その映画を見もしないで、その監督や出演者の名前だけで勝手に判断して事足れりとする態度である。
たしかに我々はさまざまな対象、情報、主張に毎日さらされる生活を送っており、それらに対する判断をするのに常に時間的な余裕があるとはかぎらない。
つまり、いちいち箱を開けて中身を実際にチェックしている余裕があるわけではない。届くすべての封筒の封を切って、中身を読んでいるわけではない。送り主、差出人(出どころ)だけ見てだいたいの見当をつけているだけなのが普通だろう。
当然、箱も開けずに、封も切らずに大ざっぱな判断を下して片づけている場合が多いはずだ。かくいうこの私もそうだ。
では、そうしている人間はみな “出どころによる判断” のトリックを使っていることになるのだろうか?
いや、違う。
問題はこうである。
ある本が出版されたとしよう。その本を読まずに、その著者の名前(出どころ)だけで主観的な印象を持ったり、自分なりの見当をつけることはあるだろう。そこまでならいいのだ。
ところが、その本を読みもしないで、自分の主観的な先入観だけで判断を下して書評を書いたらどうなるか?たとえば、「この著者の妻は中国人だ」 とか、「この著者はこういった経歴の持ち主だ」 などといったことを根拠にその本自体の評価を下す場合は、“出どころによる判断” のトリックとなるのだ。
平たく言うと、主観的な先入観で勝手に想像してしまうことはよくあり、実際ほとんど不可避である。また、そこまでならば、いくらやってもかまわないのだ。しかし、それをそのまま不用意に言葉にして発表したり、公開したりしてしまうと、知的ルールの一線を越えた無責任な行為となるということである。
実際の例では、この一線を気づかれずに越えるために実に巧妙な手口が使われている。たとえば、「この記事の著者はクリスチャンだから」 とか、「この映画の監督は韓国人ですからね」 などといった、まことしやかなほとんど差別的な判断がなされることがある。
さらに 「この本の著者は陰謀論者だから」 とか、 「この動画の作者はオカルト信者だから」 とか、 「この曲の作者は元々が歌手くずれだから」 とかいった “ラベル貼り” や “人身攻撃的なケース” もある。
また逆に、「この絵を描いた画家は芸大出だから」 とか、「この製品を推奨しているひとは東大の教授だから」 といった盲目的な権威主義を振り回して絶賛する場合もあるのだ。



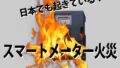
コメント