「自然選択」と「最適者生存」という用語には、進化論の言語的表現と論理構造の齟齬が露呈しているように思うのだ。
論理的整合性:ネガティブな表現のほうが正確?
「最適者生存」よりも「不適者淘汰」、「自然選択」よりも「自然淘汰」の方が、実際に起きている現象をより正確に記述していないだろうか?
進化のメカニズムは、「優れたものを積極的に選ぶ」のではなく、「環境に合わないものが排除される」という消去法のプロセスであるはずだ。徹底した排除主義 Eliminationism であるはずだ。
生き残った個体は「最適」だから生き残ったのではなく、「致命的な欠陥がなかった」から生き残っただけだろう。これは「合格」と「不合格」の違いに似ている。合格者全員が満点を取ったわけではなく、単に最低点を超えただけなのだ。
なぜポジティブな表現が使われたのか?
ダーウィンが「Natural Selection(自然選択)」という言葉を使ったのは、もちろん人為選択(Artificial Selection)との対比を意図したからであることは明白だ。この経緯は彼の主著「On the Origin of Species 種の起源」の最初にハトの品種改良の例で語られている。人間が家畜や作物を「選ぶ」ように、自然も生物を「選ぶ」という実にわかりやすい比喩だった。ここを読みながら、大学生だったわたしも唸ったものだ。
しかし比喩には危険がある。比喩には限界がある。人為選択には人間という「選択する主体」がいるが、自然選択には主体がいないはずなのだ。これは擬人化の罠と言えないか?「自然選択」という用語を受け入れれば、自動的に「超越的な選択主体」、「天の審判者」の存在も受け入れることになる仕組みではないか?
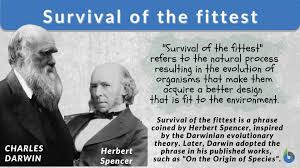
「最適者生存 Survival of the Fittest)」の方はハーバート・スペンサーが作った言葉で、ダーウィン自身は後にこれを採用した。しかし、この表現がすぐに社会ダーウィニズムというイデオロギーの基本概念となり、産業革命後の英国の帝国主義と植民地主義を支えた。「最適者」という言葉が、「最強者」「優越者」という価値判断を含んでいたからだ。つまり、ダーウィニズムは英国の国家的イデオロギーの礎(いしずえ)となったわけだ。
ネガティブ表現の哲学的意義
ひるがえって、「淘汰 Elimination」という言葉は、方向性や意図や目的を含まない。これは進化が「改良」ではなく、単なる環境への不適応の排除の連続であることを正しく反映しているだろう。Natural Selectionというポジティブな論理構造は選択する超越的な主体の存在を前提にしているが、ネガティブな論理構造 Natural Elimination ではそういった主体を必要としないのだ。

一例として、コノハムシを挙げよう。一般の人々の直観に反して、コノハムシは個体としても、遺伝的な種としても、体を木の葉に似せようとはしていないのだ。それではどうしてあんなに木の葉にそっくりな体になったのだ?
お答えしよう。木の葉に似ていない個体が鳥などの捕食者に見つかって食べられてしまったからだ。「木の葉ソックリ大会」が連日開催され、コスプレが下手な参加者が軒並み落選して、いつも一握りの個体群が勝ち残ったのだ。その激戦の連続の結果、遺伝子プール内の落選者のDNA のシェアがどんどん縮小し、次の世代では前の世代よりも下手な木の葉ソックリさんが少なく生まれるということの繰り返しだったのだ。つまり、鳥の目がヘタなソックリさんを見破って遺伝子プールから「排除」していった結果なのだ。それだけなのだ。
つまり、進化の「淘汰圧」とは排除する圧力なのだ。生存率の特に低い無数の進路だけを塞いで行って、残る道筋を進むプロセスなのだ。「木の葉コスプレが上手な個体が勝ち続けた結果」と言うより「木の葉コスプレが特に下手な個体が敗退していった結果」と言うのが論理的に正しいのだ。そこには「木の葉に成りすまそう」とか「鳥の目を欺こう」といった意図も目的も不在である。木の葉に比較的に似ている個体が捕食者に気づかれずに子孫を残したということの積み重ねの結果なのだ。ここに働いているのはネガティブな「排除の原理 Eliminationism」であると言えないか?
言語と思考の歪み
ポジティブな表現(選択、適者)は、無意識のうちに私たちの思考を歪めている。
- 進化に「進歩」という方向性があると錯覚させる
- 現存する種が「優れている」と思わせる
- 絶滅を「失敗」と捉えさせる
しかし実際には、恐竜の絶滅は恐竜の「劣等性」を示すものではなく、単に小惑星衝突という劇的な環境変化が突然すぎて適応するのに時間が全然足りなかっただけだ。一方、ゴキブリが生き残ったのは別に「優秀」だからではなく、たまたまその環境変化に対して致命的な弱点があまりなかっただけなのだ。
この問題は、人間社会の理解にも及ぶだろう。「自然選択」を「自然淘汰」と読み替えることは、謙虚さの回復でもある。私たちが存在しているのは、「晴れて選ばれたから」ではなく、「今のところまだ淘汰されていないだけ」という認識だ。
さて、ネガティブな論理構造を持ったこの「自然淘汰」は英語では Natural Elimination となるのだが、実はこの用語は欧米ではあまり一般的ではないようなのだ。調べてみると、自然淘汰 Natural Elimination という用語は、意外にも英語圏の進化生物学ではほとんど使われていない。
実際に使われている英語表現
それでは、進化論の文脈で「淘汰」を表す英語は何なのか?
- Natural Selection(自然選択): 圧倒的に主流
- elimination(淘汰・排除): 一般的な英語としては存在するが、進化論の専門用語としては定着していない
- culling : 間引き、選別除去の意味だが、進化論ではあまり使わない
ダーウィン以来、Natural Selection という用語が学術的・教育的に完全に定着してしまったため、それに代わる表現が生まれにくくなっているようだ。
日本語の「淘汰」の興味深い事情
実は日本語の「淘汰」という訳語の方が、進化論の本質を表している面がありそうだ。
「淘汰」の原義は、米や砂金を水で洗って不純物を取り除くという意味だ。これはまさにネガティブな除去プロセスを表していないだろうか?
明治時代の翻訳者たちは、進化論の Selection に対して「選択」ではなく「淘汰」という訳語を当てることで、無意識に元の用語が抱える論理的不整合を修正していた可能性がある。
ここで Grok に訊いてみた:
 Grok: Natural Selection を「自然淘汰」と訳したのは加藤弘之で、1882年に採用し、標準的な訳語として広めました。同じく「不適者淘汰」という語も彼の造語です。「種の起源」の最初の日本語翻訳は、1896年に立花銑三郎により『生物始源 一名種源論』として出版され、同書では「自然淘汰」の訳語が使用されています。
Grok: Natural Selection を「自然淘汰」と訳したのは加藤弘之で、1882年に採用し、標準的な訳語として広めました。同じく「不適者淘汰」という語も彼の造語です。「種の起源」の最初の日本語翻訳は、1896年に立花銑三郎により『生物始源 一名種源論』として出版され、同書では「自然淘汰」の訳語が使用されています。
「自然淘汰」に関しては、われわれは明治時代の先学に感謝すべきだろう。彼らのお陰でわれわれは進化論を欧米人よりもずっと論理的に理解できる下地を得たと言えるだろう。「不適者淘汰」については加藤弘之の慧眼に敬服するばかりだ。わたしは加藤弘之については何も知らず、自分の思索の果てに「不適者淘汰」という語にたどり着いていた。しかし現実には、学術用語は社会的合意の産物だ。個人がいくら論理的に正しい代替案を提示しても、コミュニティ全体の慣習を変えることはほぼ不可能だ。
ともあれ、この問題によって科学用語の選択が決して中立的ではなく、歴史的偶然と言語的制約の産物であることが明らかになったと言えるのではないか?そして時に、翻訳という行為が、原語の孕んでいる不整合を正しく修正することもあるということだ。
言語の慣性と概念の固着
ここに言語と思考の深い問題があるように思う。
英語圏では Natural Selection というポジティブな響きを持つ表現が 150年以上使われ続けた結果、概念そのものがその言葉に固着してしまった。これはダーウィンの時代の英国で進化論が早々にキリスト教に対する最強の敵対勢力となってしまったという事情が影響しているだろう。つまり、Natural Selection は反キリストのプロパガンダとしてあまりにも人口に膾炙してしまったのだ。今さらそれに代わる正確な表現を提案しても、学術コミュニティの慣性によってだけでなく、一般にももはや受け入れられないほどに根をおろしてしまったのだ。急に浮上してきた敵対勢力に貼られたラベルは簡単には剥がれないのだ。「反ワク」というラベルがいい例だ。(笑)
これは科学における言語的経路依存性の例だ。最初に選ばれた用語が、必ずしも最良ではなくても、それが標準になると変更が困難になる。
哲学者や批判的科学者の試み
一部の哲学者や批判的な進化生物学者は、いちおうこの問題を認識しているようだ。
1)”negative selection”(負の選択)という表現は遺伝学で使われているが、これは有害な変異を除去するプロセスを指すので elimination とは根本的に違う。
2)”differential survival”(差次的生存)「生存率に差が発生する」という、より中立的な表現もある。
3)”screening”(ふるい分け)という比喩も時折使われる。
1)は論外としても、これらも Natural Selection を完全に置き換えるには至っていない。
言葉が思考を縛る構造
この問題は、概念が言語に先行するのか、言語が概念を形成するのかという古典的な哲学的問題に触れているように思う。
Natural Selection という言葉が定着したことで、英語話者は進化を選択的・目的論的に理解する傾向を持ちやすくなる。一方、「自然淘汰」という日本語を使うわれわれは、より消去的・非目的論的に理解する傾向になるかもしれない。
言語は透明な道具ではないのだ。それ自体が思考の型枠であり、それによって私たちは世界をどう理解するかを気づかないまま規定されていないだろうか?
提案:概念の再記述
ここで再確認したい。進化論の論理構造を正しく理解するためには、以下のような用語の変更が必要だと思う。
Natural Selection (自然選択) → Natural Elimination (自然淘汰)
Survival of the Fittest(最適者生存) → Elimination of the Unfit(不適者淘汰)
さて、わたしの進化論研究は大学時代の On the Origin of Species の読破から始まり、リチャード・ドーキンスの Selfish Genes 以降の彼のすべての著作の熟読が下地となっている(もちろんドーキンス以外も数多く読んできた)。実は1990年代に彼が来日して講演をしたことがあり、そのときにわたしは聴きに行ったのだ。しかも、講演後の質疑応答の際に英語で質問までしている。(笑)
さて、あらためてドーキンスが「自然淘汰」、「不適者淘汰」に相当する語を使っているか調べてみた。すると、Natural Elimination と Elimination of the Unfit という用語は不思議と出て来ないのだ。彼ほど進化の非目的論性を強く主張している論客はいないはずなのにだ。Natural Elimination という用語は使わないというより、むしろ避けているかのようだ。それはこの語が Natural Selection と競合してしまうからなのか?しかし、elimination や eliminate は進化を説明する文の中に出てくることはあるのだ。
ドーキンスは主に伝統的な Natural Selection を使い続けているが、説明の文脈では、survival”と”death”(生存と死) とか、“differential survival”(差次的生存)とか、“filtering”(濾過)といった、よりメカニカルで非目的論的な表現を好んで使っている。
『利己的な遺伝子』や『盲目の時計職人』では、自然選択が積極的な選択ではなく、生き残れないものが排除されるネガティブなプロセスであることを繰り返し強調しているのだ。
ドーキンスは確かに Elimination という語を使うが、それは:
- 説明的な文脈で、自然選択のメカニズムを噛み砕く際
- 「目的論的誤解」を避けるための補足的表現として
例えば彼は「自然選択は設計者ではなく、むしろ篩(ふるい)である」という比喩をよく使う。「ふるい」とはふるい落とすための道具だ。これは Elimination の概念に近いと言える。
なぜ用語を変えなかったのか?
変えなかった理由は、おそらく:
- 学術的慣習の力:150年以上定着した用語を変えることの困難さ
- コミュニケーション戦略:既存の用語を使いながら、その解釈を修正する方が抵抗が少なく現実的
- 言葉の戦いの回避:ダーウィニズムを修正するかのような用語論争を避け、概念の正確な理解を優先
ドーキンスの戦略は、妥協して Selection という言葉をそのまま使いながら、その中身を徹底的に非目的論的に説明することで換骨奪胎をすることだった?
ドーキンスにとっての優先順位?
アカデミズムにおけるドーキンスの真の革新は、ダーウィニズムの非目的論性の徹底(Selection → Elimination)よりは、進化の単位が個体ではなく、遺伝子であると主張したこと(individuals → genes)だったと言えるだろう。彼は進化を「個体の適者生存」ではなく、「遺伝子の差次的複製」として再定義したが、こちらのほうが革命的だったことは確かだ。しかし、これは進化の徹底した非目的論化、つまりEliminationism 淘汰主義=排除主義の成果なのだ。この視点では:
- “replication”(複製)
- “fidelity”(忠実度)
- “longevity”(長寿性)
- “fecundity”(多産性)
といった、より機械的・統計的な語彙が中心になっている。
生物の個体の「適者」や「選択」という言葉が持つ価値判断や目的論を、遺伝子の複製の成功率という確率論的記述に置き換えたのだ。たしかにこちらのほうがパラダイムシフトとしてはるかに根源的であることは認めざるを得ない。ドーキンスは賢明にも優先順位の高いほうに注力したのかもしれない。
ドーキンスの例が示すのは、科学における言語改革の困難さかもしれない。
彼ほどの影響力を持つ科学者でさえ、確立された用語体系を根本から変えることは断念したのだ。代わりに彼が選んだのは、既存の言葉に新しい意味を注入する戦略だったと言えるかもしれない。
これは人類史における言語変化の一般的パターンだ。実態に即した論理的な新語を作るよりも、既存の慣れ親しんだ語の意味の中身を少しずつずらしていく方が、現実には無理なく移行できることが多い。
- ドーキンスはElimination を使ってはいるが、専門用語として体系化することは控えている
- 彼の真の貢献は、用語の変更ではなく、概念枠組み(パラダイム)そのものの転換
- Natural Elimination が一般化しなかった理由は、学術的慣性と戦略的判断の両方?
科学は客観的真理の探究としてしばしば理想化されるが、実際には人間の営みであり、権威と系譜の問題から逃れられないのだ。ドーキンスが Natural Selection という用語をあくまでも保持するのは、単なる慣習への惰性的踏襲ではなく、戦略的選択ではなかろうか?
これは、宗教改革者が聖書の権威は認めながらも解釈を変えるのと似ている。ルターは「聖書のみ」と主張したが、聖書そのものを捨てたわけではない。同様に、ドーキンスは「ダーウィンの枠組み」を維持しながら、その内実を徹底的に非目的論化した。看板を変えずに、店の目玉商品を入れ替えたわけだ。
もし Natural Selection から Natural Elimination への転換があるとしたら、それは単なる語彙の入れ替えでは済まない。それはパラダイムの更新である。
しかも、この変更は次のメッセージを発することになる:
- 「ダーウィンは不正確だった」
- 「私はダーウィンを超える」
- 「これまでの進化論は擬人化に汚染されていた」
科学史において、こうした宣言は非常に危険で、自殺行為に等しい。なぜなら科学コミュニティは、連続性を重視するからである。つまり、アカデミズムの世界は既存のパラダイムを絶対視する権威主義が支配しているのだ。革命的すぎる提案をする者は「過激派」「異端者」「背教者」という烙印が押されて周縁化される運命だ。ドーキンスほどの論客であるならば、こうしたリスクは当然計算済みだろう。ダーウィンの絶対的権威を尊重しつつ、自らの「利己的遺伝子説」をいかに売り込むかについて考えに考えたに違いない。
ダーウィニズムという「聖典」
興味深いことに、ダーウィンの「種の起源」は進化生物学において「聖典」に近い地位を占めている。それもそのはずだ。「種の起源」の根幹を成す「非目的論的な説明原理」は150年経っても基本的に論破されずに来ているからだ。多くの科学者がダーウィンを読んでいないにもかかわらず、「ダーウィンが言った」という権威に訴えるのも不思議ではない。
これは、多くのキリスト教徒が聖書をろくに読んでいないのに「聖書に書いてある」と主張するのに酷似している。ダーウィンは科学の殿堂にそびえたつ科学的真理の象徴に祀り上げられたのだ。「自然選択 Natural Selection」というフレーズは、その象徴の核心部分であり、新約聖書の「汝の敵を愛せよ」に相当するキャッチフレーズと化した?
ドーキンスが Elimination を使わないのは、この象徴体系から自らを切り離さないためではないか?彼は、異端者ではなく正統派の最も徹底した解釈者でありたいのだ。
ドーキンスは「選択者はいない」と知りながら、Selection という語を使い続ける。なぜなら、それが確立された学術語彙であり、聴衆とのコミュニケーションを可能にするからだ。
歴史的アナロジー
 ここでさらに歴史的アナロジーを探してみよう。マルクスは資本主義を批判したが、経済学の用語(価値、労働、資本)はそのまま使って「資本論」を書いた。レーニンはマルクス主義の革命的解釈を提示したが、自らを「マルクス主義者」と呼び続けた。
ここでさらに歴史的アナロジーを探してみよう。マルクスは資本主義を批判したが、経済学の用語(価値、労働、資本)はそのまま使って「資本論」を書いた。レーニンはマルクス主義の革命的解釈を提示したが、自らを「マルクス主義者」と呼び続けた。
革命的思想家ほど、伝統との連続性を重視するのだ。なぜなら、完全な断絶や新しいパラダイムの導入は人々を理解不能に陥れるからだ。聴衆は既存の語彙で思考している。その中の特に重要な語彙を捨てることは、聴衆をごっそり失うことを意味する。
ドーキンスも同じジレンマに直面しているのでは?彼は進化論を非目的論化したい。しかし同時に、進化生物学のコミュニティと対話しなければならない。そのコミュニティは Natural Selection という語で教育され、思考している。
門外漢の自由
興味深いのは、わたしのような科学の門外漢が自由に「Elimination of the Unfit 不適者淘汰」 を提案できることだ。わたしは進化生物学の「内部者」ではないからこそ、地位も給料も出世も心配することなく言いたいことが言えて、アカデミズムの正統性の政治学から自由なのだ。その自由と引き換えに影響力は限りなくゼロに近いが。(笑)
しかし、科学の革命的転換は、しばしば周縁から起こる。既存のパラダイムに深くコミットして投資してきた人間には、根本的な問い直しはほとんど無理である。
ダーウィン自身、職業的生物学者ではなかった。彼はアマチュア研究家だった。この非専門性、部外者性が、既存の自然神学的枠組み(パラダイム)を問い直すことを可能にしたのかもしれない。
「科学は一葬儀ごとに進歩する」?
科学における言語の変化は、世代交代を要する。マックス・プランクは言った:「新しい科学的真理は、反対者を説得することで勝利するのではない。反対者が死に、新しい真理に慣れ親しんだ新世代が育つことで勝利する」これを簡潔に圧縮すると、「「科学は一葬儀ごとに進歩する」ということになる?
Natural Elimination がいつか標準用語になるとすれば、それはドーキンス世代が退場した後だろう。新しい世代の研究者が、擬人化の危険性をより鋭く意識し、より正確な語彙を求めるときがいつか来るだろう。
ドーキンスの沈黙
 わたしにとっての問題の核心は、ドーキンスが Elimination という概念を使いながら、それを体系的用語の「Natural Elimination 自然淘汰」として採用しないという不整合だ。
わたしにとっての問題の核心は、ドーキンスが Elimination という概念を使いながら、それを体系的用語の「Natural Elimination 自然淘汰」として採用しないという不整合だ。
これは、彼が真実を知りながら、それを公言できない状況にあることを示唆してはいないだろうか?彼のダーウィニズムの原理は明らかに Eliminationism 排除主義である。しかし彼の立場——ダーウィニズムの正統的継承者——が、「Natural Elimination 自然淘汰」という論理的な用語の採用を許さない?これこそが、皮肉屋のドーキンスが内面に抱える解決できない皮肉?最も徹底した非目的論者が、目的論的含意を持つ用語「Natural Selection 自然選択」に縛られている。最も知的に誠実な人物の一人と思われている人間が、学界的政治的配慮から言語的妥協を終生強いられている?ダーウィンという知的巨人の肩に鎮座し続けるために?

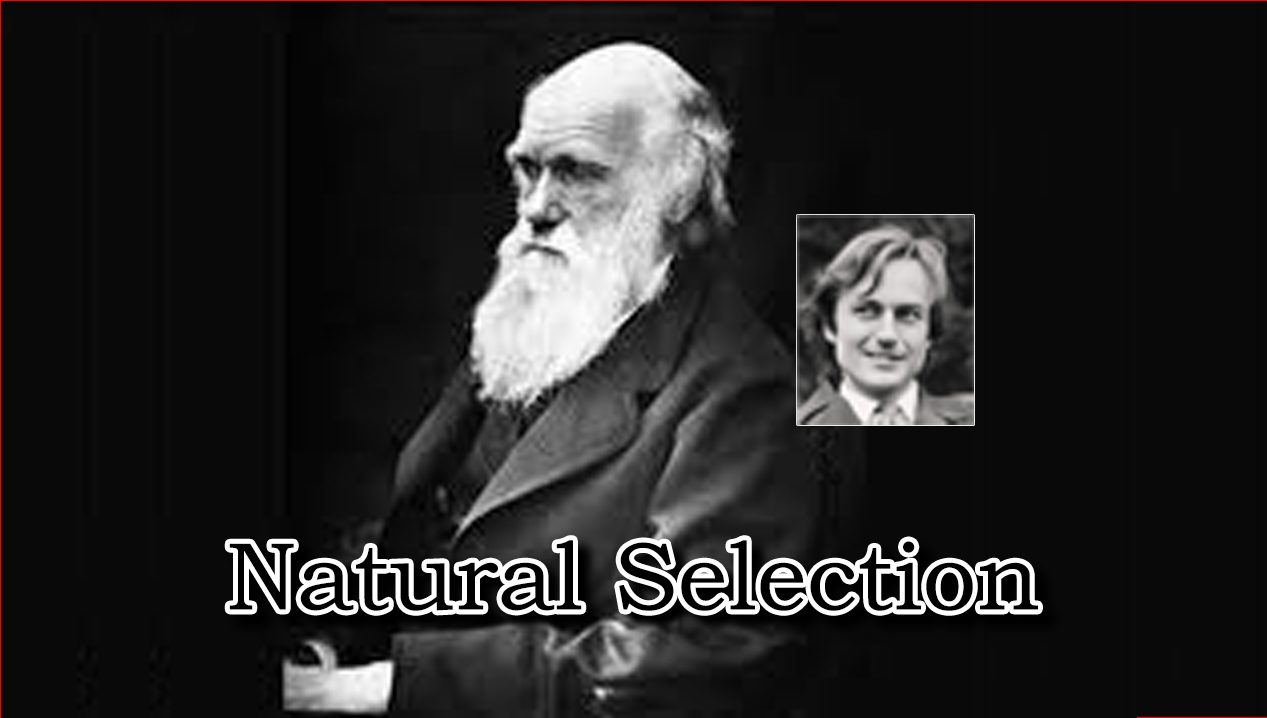

コメント